トラス橋
◆トラス橋のはじまり◆
トラス構造形式は、古くは14世紀のヨーロッパではすでに建築家たちによって提案されていました。16世紀には、構造が簡単で加工しやすい木造のトラス橋が各地で見られるようになりました。
また、桁橋より長いスパンを確保できることから、トラス橋は19世紀の中頃以降、鉄道の急速な発展とともに、世界中で架設されていきました。道路用の橋としても、特にアメリカでは、木造ながらトラス橋が盛んに建設されました。
今日でもトラス橋は、アーチ橋と並んで広く採用される一般的な構造形式となっています。
◆トラス橋の原理◆
三角形は三つの辺の長さが決まると形が決まり、安定した構造が得られます。柱と梁で出来た四角形の中に筋交いを入れ、三角形の組み合わせにすることで丈夫になります。
この構造をトラス構造と呼び、このトラス構造を組み合わせて造る橋をトラス橋と呼びます。実際に用いられているトラス構造には部材の組み方によって色々な種類がありますが、その多くは考案した人の名前がつけられています(ワーレントラス、プラットトラス、ハウトラス等・図参照)。
トラス構造は軽くて丈夫なため、支間の比較的大きな橋に用いられますが、橋以外でも建物の柱や屋根、鉄塔等、様々な建造物に用いられています。代表的なものには東京タワーがあります。

2011(平成23)年の開通が予定されている「東京港臨海大橋(仮称)」の完成予想イメージ。この大橋の開通によって、臨海部の物流、東京湾岸道路の混雑もスムーズになることが期待されています。
羽田空港に隣接し、空域の高さ制限があるため、レインボーブリッジやベイブリッジなどの吊り橋や斜張橋のような高い主塔を必要としない「トラス橋」が採用されました。
◆日本のトラス橋◆
我が国では、明治初年から鉄道橋としてのトラス橋が建設されました。1871(明治4)年には、新橋・横浜間の鉄道が六郷川(多摩川)を渡る場所にトラス橋が架設され、1874(明治7)年に開通した神戸・大阪間の鉄道には、我が国で初めての錬鉄製の鉄道橋が架設されました。これは、神崎川、十三川、武庫川を渡る橋梁で、いずれもスパン約21mのワーレントラスでした。これらはすべてイギリスで製作され、日本に輸入されたものです。
トラス形式では、最長で500m位までの長さを途中で支えることなしに渡すことができます。山間部や、港
の横断に連続トラスが採用されてきました。港を渡る場合は、あらかじめ岸壁でトラスを大きなブロックで組み立ててから、クレーン船で吊り上げて架設する方法も採用されました。最近では東京港臨海大橋(約7000トン)が3艘のクレーン船で一括架設されています。

日本最初の国産橋で2番目に古く現存する八幡橋(旧弾正橋)
1878(明治11)年に東京の楓川に架けられた橋長15・1mのボーストリングトラス形式の弾正橋は、関東大震災後の復興計画により1992(昭和4)年に撤去となり、江東区深川の富岡八幡宮の境内の裏側に移設され、名を八幡橋と改めて人道橋として再生されました。1950(昭和25)年に国指定重要文化財となり、大切に使われています。
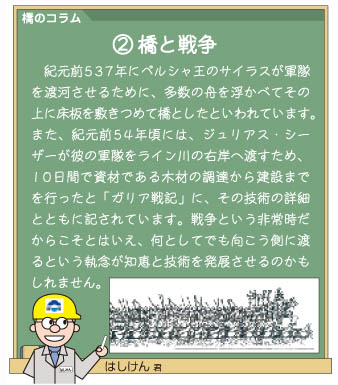
|